はじめに
私は24歳で事故に遭い、頸髄損傷を負いました。病院や施設での生活、家族による介護の時期を経て、「自分の暮らしを自分でつくりたい」という思いが強くなり、一人暮らしを始めました。そこから重度訪問介護の利用者として、介護士(ヘルパー)さんに日常の介助をお願いする生活が始まりました。
利用者として直面した現実
一人暮らしを始めたばかりの頃、正直に言えば私は「介護士(ヘルパー)さんの介助は仕事なんだから、頼んだことはできて当たり前」「苦手でも努力して当然」「言った通りにできないのはおかしい」と考えていました。
頭では「介護士(ヘルパー)さんも一人の感情を持った人間である」と分かっていても、実際に自分のことをやってもらうにあたって、思い通りに進まないと苛立ち、「なぜ言ったようにやれないんだ」と感じることが多くありました。今振り返ると、まるで感情を持たないロボットのように扱っていたように思います。相手の気持ちや得意・不得意、一人の人間としての感情や主体性を十分に見ようとしていませんでした。
当然、関わりはうまくいきません。介護士(ヘルパー)さんたちが気に入らない態度を取ったり、ある日、何も言わずに辞めてしまうことが続きました。辞める前も後も理由を語らないまま去られることがほとんどで、「何がつらかったのか、何が嫌だったのか」がわからない。残るのは「なぜこんなにうまくいかないんだろう」「なぜなんだろう」と悩む自分だけでした。
そしてある時、自分自身の態度はどうなんだろうと考えるようになりました。自分自身が考え方を改めて、ものの言い方、伝え方、人間関係の築き方などを見直していく必要があることに、ようやく気づいたのです。
「どう伝えるか」「いつ伝えるか」の大切さ
例えば掃除ひとつとっても、私は「ここをこうして」と結果ばかり求めがちでした。でも実際には「どこから始めるか」「どの道具がやりやすいか」「こうすると負担が少ない」など、段取りと方法をすり合わせることが必要でした。
ダメ出しを重ねるより、「どう進めたらやりやすいですか?」と最初に話し合う。そのほうが結果もスピードも良くなるし、お互いの関係も穏やかになることを実感しました。
強い口調や、忙しさの勢いで言ってしまった一言は、相手に窮屈さを残します。だからこそ「何を伝えるか」だけでなく、「どう伝えるか」と「いつ伝えるか」を大事にする。私にとっての基礎がここでできました。
事業所設立への道のり
やがて障害者の介護制度が措置制度(行政がサービスの利用先や内容を決める)から支援費制度(障害者本人の自己決定に基づきサービスを利用する)に変わり、これまでの形では介助を確保できなくなったため、自ら事業所を立ち上げる道を選びました。
現在の事業所「かむしぃ」(介護事業所名:らっぽると)は小規模です。小さいからこそ、介護士(ヘルパー)さん一人ひとりの関わりが、利用者さんの生活の質にそのまま直結します。
ここで新たな課題が生まれました。自分が利用者であり、同時に雇用主でもあるという二つの立場があることに、最初は気づけていませんでした。自分では雇用主として、「自分のことを通して利用者にも役に立つ」という理由で、一つのことに完璧にできるようになるまでそのことだけにこだわったり、「うちの考えはこうだから」とスタッフに従わせるような態度を取っていました。
しかし、介護士(ヘルパー)さんは、雇用主である私の指示に萎縮してしまい、余計に何も言えなくなるということを考えもしていませんでした。結果、介護士(ヘルパー)さんは言いたいことを飲み込み、沈黙が増え、そして沈黙のまま辞めていく。本当ならもっと介護士(ヘルパー)さん一人ひとりの態度や行動に注意深く目を向けておくべきでした。この連鎖に気づくのが遅れたのは、大きな反省点です。
感情がぶつかったときの向き合い方
人同士の関わりですから、感情が出る場面は避けられません。スタッフの性格によっては、態度に感情をそのまま出してしまう人もいます。ちょっとした言い合いになることもあります。
でも、感情が高ぶっているときに建設的な話は進みません。そこで私は、その場で結論を急がないことを選びました。いったん距離を置き、落ち着いたタイミングで、改めてその時の話をするようにしています。
その話し合いの中でよく出てくるのが、雇用主としての立場と利用者としての立場に挟まれているという複雑さです。私自身、この二つの立場の間で揺れ動いていることを、スタッフである介護士(ヘルパー)たちとの対話を通じて改めて実感しました。
その時に話し合うのは、人の良し悪しではなく、具体的な行動・やり方・場面です。「あの時、こう言われてこう感じた」「こういう進め方ならやりやすい」「ここは優先順位を変えたい」。感情の温度が下がって初めて、言葉が届き合います。
こうした介護士(ヘルパー)さんたちとのやり取りを繰り返していくうちに、自分自身が介助をしてもらうときに、**「その都度、言いたいことがあれば遠慮なく言ってください」**と伝えるようになりました。お互いが遠慮せずに話せる関係を築きながら、日々私も一緒に成長していこうと心がけています。
他の利用者さんのもとで大切にしていること
かむしぃでは、介護士(ヘルパー)さんが他の利用者さんのもとへ伺う機会も多いです。その時に求めているのは、ただ作業をこなすことではありません。**「かゆいところに手が届く」**こと。つまり、その方の生活や習慣、望むペースに寄り添うことです。
もちろん、コミュニケーションで難しい場面もあります。基本的なことでも見落としがちで、そこで食い違いが起こることがあります。私が代表として注意をお伝えすることもありますが、ここで誤解されやすいのは「あなた個人を責めたいわけではない」という点です。
私が見ているのは、目の前の利用者さんの暮らしです。介護士(ヘルパー)さん一人ひとりが、自分の対応に自信を持てるように——そのための指摘です。ここは、伝え方をさらに磨き続けたいところでもあります。
「時間をかける」ことの価値
介護の現場で起きる課題は、すぐに答えが出るものばかりではありません。価値観、身体状況、生活リズム、言葉の使い方。いろいろな違いが絡み合うからこそ、対話には時間が必要です。
私は、時間をかけて向き合うこと自体が、課題を解くプロセスであり、成長の機会であり、お互いを理解し合う最も大切な要素だと実感しています。
効率よく”片づける”より、必要な時間を惜しまない。遠回りに見えて、これが結局いちばん確かな前進だと、現場に立って感じています。小規模な事業所だからこそ、この時間を確保できる。これが、かむしぃの基盤です。
いまの私の立ち位置と、これから
私は重度訪問介護の利用者であり、介護士(ヘルパー)さんを雇う事業主でもあります。二つの立場の間で悩み続けるからこそ、利用者さんのリアルな声と、働く人の大変さの両方を見続けることができます。
失敗も反省も、現場での会話も沈黙も、その都度すべて積み重ねて、暮らしを一緒につくる方向へ少しずつ舵を切っていきたいと思っています。
「かむしぃ」(運営法人:らっぽると)は、小さな事業所です。小さいからこそ、一人ひとりに目を向け、時間をかけ、共に学び、共に前へ進む。その姿勢で、これからも介護の現場に向き合っていきます。
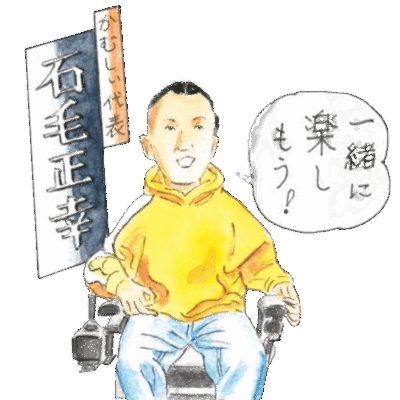
かむしぃについてもっと知りたい方、介護のお仕事に興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。一緒に「暮らしをつくる」仲間をお待ちしています。
